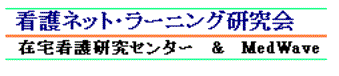
21世紀は人作りが大切と感じています。プロフェッショナルの多い医療界では、そのプロを指導する人が必要です。しかし、この指導者がなかなか見当たらない。在宅看護の分野では幸いにして、地道に実績を積み上げてきたグループがあります。在宅看護研究センター・村松さんのところには、もったいないくらいの人材養成のための資産と実績があるのです。私はもう6年近くになりますが、長い間、村松さんらの活動を見てきた一人です。その確かな信念とたゆまない努力、環境に立ち向かう勇気、時には挫折する姿も見ましたが、一貫して揺ぎ無かったことは、患者さん中心の看護、医療を提供しようという姿勢でした。主体が株式会社であれ医療法人であれ個人であれそれは変わらないことなのです。そしてなにより驚いたことは、人作りにすでに取り組まれていたことです。培われたノウハウは本物です。それは、広く伝えていかなければならないものです。人材養成の発信源として、この研究会を立ち上げたのです。村松さんも同じようにお考えでしたので、すんなりと決まった次第です。
現在行っていること、考えていることについて
看護分野でのネット・ラーニングは、忙しすぎる看護職にある方には欠かせないものになるはずです。なぜなら、いつでも好きなときに、好きなものを、好きなだけ学べる手段がそこにはあるからです。教材はインターネットのホームページ上におかれているので、ホームページにアクセスできる環境であれば、自分の好きなときにテキストを学べるわけです。疑問点は直ちに講師にメールで送ることができます。また、受講者同士のディスカッションは、メーリングリストというインフラを使えば、通常のメールでみんなに送信することができるのです。現在、実験的な位置付けでもありますが、この看護分野でのネット・ラーニングの実証実験を進めております。それが「在宅看護論の教授法エッセンス」なのです。
今後、さらに行いたいこと
看護分野に限らず、医療・医学、介護の分野でも同じようなネットラーニングに取り組みたいと考えています。来年からは、動画コンテンツの配信がやすく手軽にできるようになるはずです。そうすると、通常の講演、セミナー、研修をそのままデジタルビデオに収録して、それを編集しなおしてホームページ上で提供することが可能になります。看護、医療・医学、介護分野ほど、動画情報が必要な分野はないのです。動画配信、受信のインフラが整えば、今のテレビ以上に鮮明な画像情報を提供しつつ、リアルタイムで教育・研修番組を提供することも可能になるはず。結果をライブラリーとして蓄積していけば、それこそ「いつでもだれでも、好きなものを好きな時間に、好きなだけ学ぶ」ためのコンテンツを用意できるわけです。それはいずれは、日本の医療水準を高めることにつながるはずです。私は、その先鞭をつけたい。新しい教育、自己研修方法を開拓したいと考えています。
日経BP社と在宅看護研究センターの役割分担
以上の夢を現実のものとするためには、優秀なコンテンツを開拓する必要があります 。日経BP社の役回りはまずそのコンテンツを探し当てることです。在宅看護分野に付きましては、村松さんのグループに出会ったことで、優秀なコンテンツに出会ったと思っています。
在宅看護研究センターの役割は、すでにある有力なコンテンツをネット対応にするだけです。
今後について予測していること(インターネット教育の可能性)
すでに書きましたが、インターネット教育は、その手軽さからかなり急速に広がっていくはずです。ただし、裏打ちとして、本当に役立つ教育情報があることがなにより必要です。
あくまでもインターネット教育は、実際の研修、教育を補完するものと認識しています。
インターネット教育だけで完結はしないという意味です。通信教育と同じで、やはり実際の研修(リアル)と密接につながっていないと成功しないと思います。その意味では、リアルとインターネットをセットで番組にできるところとパートナーを組んで、さまざまな番組を提供したいと思います。
以上、日経BP MED WAVE編集長 三和 護 氏によるお話でした。
一方、在宅看護研究センタ-代表・村松 静子氏は、
・ 編集長の熱心さに惚れ、意気投合。また、自身もその必要性を強く感じたこと。
・ 日経BP社がこのビジネスパートナーとして最も適していると感じたこと。
・編集長が教育の必要性をしっかり理解していると感じたこと。
・ 時代はIT社会。そこに、今最もほしい心をどう付けるかが問われている。そこへ挑戦したくなったから。
・いつでも、どこでも学べる補足的な看護教育をしたかったから。
・ 今後は、絶対売れると思ったから。
・ やってみたかったのよ。
と、発足にいたるきっかけを述べた。さらに、インターネット教育について
「リアルとの組み合わせが不可欠。そこを在宅看護研究センターで行っていきます。」と結んだ。
●
● ●
● ●
● ● ●
●
● ●
● ● ●
● ●
●
● ●
●
● ●
● ●
● ● ● ●
● ●
●